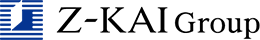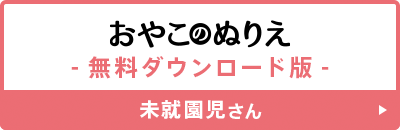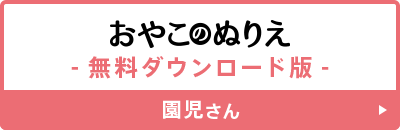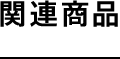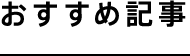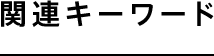受験準備
幼児期の「ぬりえ」が子どもの世界を広げる
幼児期の「ぬりえ」が子どもの世界を広げる
2019.2.12
近年、大人の自律神経を整える方法としても注目を集めている「ぬりえ」。幼稚園受験や小学校受験でもよく出題されます。子どもにとってぬりえは運筆の練習になりますし、ものの色や形を識別する力も育みます。「ぬりえ」を通じて、子どもの世界を広げるために、大人はどんなことを心がければよいのでしょうか。

指先を使い、絵や字を書く力につながる
子どもにぬりえを与えるとき、大人は見守っているだけのことが多いのですが、できれば子どもの隣に座って、相談しながら同じモチーフのぬりえを一緒に塗るのがよいですね。
大人がクレヨンの持ち方や塗り方を見せてあげることで、子どもが「大人のしていることを見て待つ」「お手本の通りにする」ことを学ぶことができます。
最初は、枠からはみ出して塗ることがほとんどかもしれません。でも繰り返し塗ることで、目と手の動きにつながりができ、いつしか枠に沿って色を塗れるようになります。これを「目と手の協応」といいます。
クレヨンや色鉛筆を思い通りに動かすことで、指先の動きが洗練されて、絵を描く力、字を書く力につながっていきます。また、色の名前も覚えることができます。

親子で会話を楽しむことで世界が広がる
子どもがぬりえをするときは、親子の会話がとても大切です。
「このあいだ動物園で見た、ぞうさんだね」
「りんごは何色だったかな?」
「バナナは〇〇ちゃんが大好きだよね」
など、絵柄を通じて親子でコミュニケーションをすることで、単に色を塗るだけではなく、子どもがいろいろなものに関心を持つようになり、世界が広がっていくのです。
このとき、つい「はみ出さないように塗ろうね」などと口を出したくなってしまいますが、子どもは、大人に言われたからといって上手に塗れるわけではありません。何度もくり返すうちに少しずつ、枠の中に塗れるようになっていくので見守ってあげましょう。
りんごやきゅうりなど、絵柄が身近なもののときは、実物を持ってきて、どんな色をしているのか観察しながら塗るのも楽しいでしょう。図鑑を調べながら塗るのもおすすめです。
電車に興味のある子は1日中電車遊びばかり、というふうに、幼児期の子どもは、同じ遊びばかりしがちです。親子でコミュニケーションをとりながら同じ時間を楽しむことで、子どもの興味の対象を広げていけるとよいですね。
-
- 大人が隣に座って、クレヨンの持ち方や塗り方のお手本を見せる。
- 枠の中を塗るのは子どもにとって難しいもの。最初のうちは、はみ出してもOK。
- 親子で会話したり、実物と比べるなど、コミュニケーションを楽しみながら塗る。
A4サイズにプリントアウトし、点線で切り離してご利用ください。
おうち時間もたのしいものになりますように。

年齢別

受験準備
小学校受験の問題集は「ちょっと簡単」くらいから始める
小学校受験では、どんな問題集からはじめたらよいのでしょうか? 小学校受験に備えた家庭学習には、子どもの習熟度に合わせた問題集を使った学習が効果的です。今回は問題集の選び方と、受験の時の大人の関わり方についてお話します。

受験準備
つみきで空間認識力を楽しく身につける
梅雨の時期は、家での遊びが中心になります。子どもが夢中になって、じっくり取り組める遊びができるとよいですね。今回は、手先をたくさん使いながら、想像力や図形センスが身につく「つみき」にクローズアップしてみましょう。
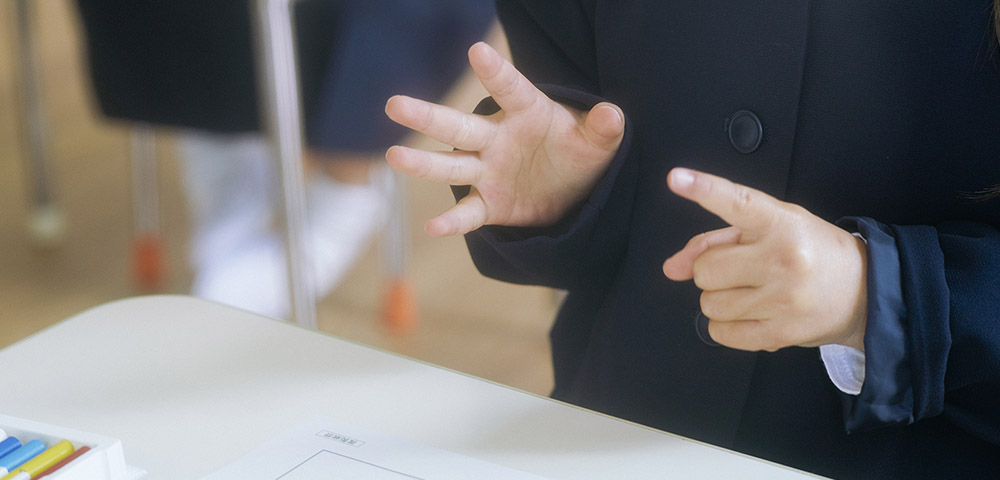
受験準備
一生役立つ算数力は生活の中で育つ
最近、「算数力」や「算数脳」というキーワードに注目が集まっています。幼稚園受験や、小学校受験でも、数に関する問題は毎年必ず出題されます。子どもが楽しみながら数を理解して、算数を好きになるために、大人はどんなことをするのが良いのでしょうか。