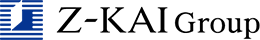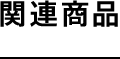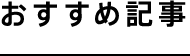受験準備
一生役立つ算数力は生活の中で育つ
一生役立つ算数力は生活の中で育つ
2019.5.24
最近、「算数力」や「算数脳」というキーワードに注目が集まっています。幼稚園受験や、小学校受験でも、数に関する問題は毎年必ず出題されます。子どもが楽しみながら数を理解して、算数を好きになるために、大人はどんなことをするのが良いのでしょうか。
暮らしの中の身近な「数」を意識する
算数力を育むためには、幼児期から足し算や引き算などの計算をさせたり、1から100までなど、多くの数を数えられるようにトレーニングするイメージがあるかもしれません。スピーディーに計算し、正解を導き出す力こそ大切だと大人は考えるからです。
もちろんそれらが必要な時期もやがて訪れますが、幼少期には、生活の中で子どもと数を意識するような会話をたくさんすることが大切です。
「8時になったから寝ようね」
「〇〇ちゃんのお家は3階だね」
「うさぎさんが4匹いるね」
「お皿にミニトマトを2個ずつ入れてくれるかな?」
私たちの生活は、多くの「数」に囲まれています。カレンダー、時計、電話番号、物の値段、エレベーターの階数表示、おもちゃや食べ物の数などを話題にしたり、一緒に数えたりしてみましょう。
モンテッソーリ教育では、幼児期の子どもが、順番や、数量の多い・少ないにこだわったり、物をしきりに数えたり、「いち、に、さん」と数詞を口に出すことに夢中になる時期を「数の敏感期」と呼んでいます。この時期に、生活の中の数を意識したり、数えたりすることをくり返すことで、子どもの算数力の土台が作られていきます。

遊びながら算数力を育む「数カード」
「数」というのは本来、抽象的なものです。生活の中にある、実際に触れられる「数」と、小学校入学後に教科書やプリントで学習する抽象的な「数」の間をつなぎ、より理解を深めるために、ICE幼児教室では、「数カード」を使った学習をしています。
「数カード」とは、1~10までの数がドットまたは果物のイラストで記されたカードです。次のような遊びを通して、子どもたちがゲーム感覚で数を正しく理解できるように、かつてICE幼児教室の教師が手作りしていたものを商品化しました。
<数カードの遊び方の例>
・人形やおはじきなど具体物と同じ数のカードを探す
・2種類のカードを並べ、どちらの数が大きいかを比べる
・カードに書かれた数を数える
・カードを数の大きい順、小さい順に並べる
・複数のカードに記された数を合わせると、全部でいくつになるか数える

量や順番を表すほか、足し引きできたり、分けることができるなど、数の持つさまざまな性質を、「数カード」を通して楽しみながら学習してみてはいかがでしょうか。
- 3~6歳の子どもには数に強い関心を示す「数の敏感期」があります
- ふだんの生活の中で数を意識する会話をしたり、数えたりすることが大切
- 「数カード」は家族で楽しみながら算数力の基礎を育むことができます
年齢別

受験準備
小学校受験の問題集は「ちょっと簡単」くらいから始める
小学校受験では、どんな問題集からはじめたらよいのでしょうか? 小学校受験に備えた家庭学習には、子どもの習熟度に合わせた問題集を使った学習が効果的です。今回は問題集の選び方と、受験の時の大人の関わり方についてお話します。

受験準備
つみきで空間認識力を楽しく身につける
梅雨の時期は、家での遊びが中心になります。子どもが夢中になって、じっくり取り組める遊びができるとよいですね。今回は、手先をたくさん使いながら、想像力や図形センスが身につく「つみき」にクローズアップしてみましょう。

受験準備
小学校受験は特別なことではない
小さいうちから子どもには、できるだけ良い環境で教育を受け、個性を伸ばしたい、という思いから、小学校受験に関心を持つご家庭も多いと思います。小学校受験をすることのメリットや、家庭でどんな準備をすればいいのかをご紹介しましょう。