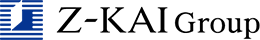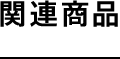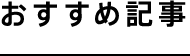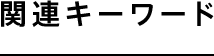子どもの力を伸ばす
「自分でしたい!」は自立の第一歩
「自分でしたい!」は自立の第一歩
2019.9.30
「母子分離」とは、親と子どもが親以外の人と過ごすことをいいます。幼稚園受験では、親と離れて別室で行動観察や質疑応答が行われることもあります。スムーズに母子分離するためには、大人はどんなことに気を付ければいいのでしょうか。
大人の手を振り払うのが自立のサイン
生まれたばかりの赤ちゃんは、大人のケアが必要なので、1日のほとんどを、親やお世話をしてくれる大人と密着して過ごします。
月齢の低いうちは、親が離れても気づかないことが多いのですが、ハイハイや伝い歩きが始まるころには、親が視界からいなくなると、泣いたり、後を追ったりすることもあります。「ママはここにいるよ」「帰ってくるから大丈夫よ」と声をかけ、必ず戻ってくることで、子どもは安心します。これをくり返しながら、親子の信頼関係が作られていきます。
やがて、自分の足でしっかり歩けるようになり、離乳が完了して食べる量も増えて、まとまった睡眠がとれるようになると、人としての自立が始まります。子どもの発達や環境によって個人差はありますが、だいたい1歳半くらいから、好奇心が旺盛になって外の世界に関心を持ち始め、少しずつ親との間に距離が取れるようになっていきます。
この時期の子どもを観察していると、大人が着替えさせようとしたり、ごはんを食べさせようとしたときなどに、大人の手を振り払い、自分で何かをやろうとする様子が見られると思います。これは「自分でやりたい」という自立のサインで、母子分離への第一歩でもあり、とても喜ばしいことです。

自立のための環境を整える
せっかく芽生えた「自分でやりたい」気持ちは尊重したいもの。少し距離を置いて、子どもを見守ることが自立を助けます。
子どもが自分で着替えたがったら、幼いうちはぬぎ着しやすいサイズを選んだり、ボタンやファスナーなどがないデザインを選ぶことも有効です。選びやすく片付けやすい場所を作ることも自立の手助けになります。
食事の時は、テーブルの周りを汚されることが親にとってはストレスになることもあります。そのような時は、汚すことを前提に子どもが自分でできる環境を整えましょう。自分で食べやすい食器を選び、こぼさずに食べられるメニューを考えるのもいいですね。いすやテーブルの高さが丁度いいか見直すことも大切です。こぼれたら自分で拭けるように用意するのも一つの方法です。
「ICEモンテッソーリこどものいえ」では、子どもたちが自分で、食事前後の台拭きや、こぼしたものの後始末などを行います。そのときに使われているのが、子どもの小さな手でも、大人と同じように拭いたり、絞ったりできる「ダスター・ミトン」です。子どもの手に合ったサイズや厚さで、手首や指先の力を育て、自分の身の回りは、自分できれいにする習慣を身に付けることができます。

自立から母子分離へ
この時期の子どもは、親から離れようとするときもあれば、泣き叫んで離れないときもあります。無理して離れさせようとしたり、厳しく叱ったりすると逆効果です。徐々に泣かずに離れられるようになるので、焦る必要はありません。
子どもを預ける時に、離れる場面で激しく泣かれたりすることもあるでしょう。親としては切なく、後ろ髪を引かれる思いですが、ここで親が不安そうにしていると、子どももますます不安になります。「大丈夫。安心して待っていてね」と伝え、預け先を信頼して任せたら、大人も覚悟を決めて、その場をサッと離れることが重要です。教室ではたくさんの子どもをお預かりしていますが、ほとんどの子どもは親の姿が見えなくなると泣き止んで、教室の環境に興味が移っていきます。
最初は泣いてばかりいても、慣れてくると少しずつ1人でいられるようになります。母子分離は焦らず、子どもの様子を見ながら少しずつ進めましょう。
- 大人の手を振り払い、なんでも自分でやりたがることが自立の第一歩。
- 子どもが自分でできる環境を用意することも大切。
- 焦ったり、叱ったりしない。子どもと離れるときは親も覚悟を決める。
年齢別

子どもの力を伸ばす
入園までにご家庭で身につけたい3つのこと
幼稚園や保育園に通うようになると、これまで家で大人が代わりにしていたことも、園では子どもが自分ですることになります。はじめて母子分離をした子どもが、自分の身支度を自分でできるようになるためには、家庭でどのようなサポートが必要なのでしょうか。

子どもの力を伸ばす
「伸びる力を育てる」プレゼントをクリスマスに贈る
クリスマスやお誕生日のプレゼント。スポンジのようになんでも吸収できる年齢の子どもこそ「伸びる力を育てる」贈り物をしませんか? 1~4歳の子どもの力を伸ばすプレゼント選びのポイントをご紹介します。