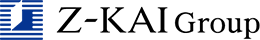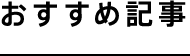子どもの力を伸ばす
叱るよりも「伝える」
叱るよりも「伝える」
2018.11.4
子どもをどう叱るか、というのは難しい問題です。「叱る」には、よりよい方向に導くという意味がありますが、親の都合で感情的に子どもを「叱る」のではなく単に「怒って」しまい、後悔した経験を持つ方も多いのではないでしょうか。今回は、子どもの叱り方について一緒に考えてみましょう。
公共の場で走り回る子どもをどうする?
たとえば、人通りの多い歩道やスーパーの中など、公共の場所で子どもが走り回ったとき、どうしますか? 周囲にも迷惑がかかるし、大人としては「危ないでしょう!」「走ってはダメ!」といいたくなります。
でも、子どもは、危ないことをしようと思って走っているわけではありません。
大人を困らせようとしているわけでもないのです。
歩行が安定してきて、走ることができるようになった時期の子どもは、とにかく走ることに夢中で、楽しくて仕方ない。ただただ走りたいのです。これをモンテッソーリ教育では「運動の敏感期」と呼んでいます。

気持ちを受け止めて、大切なことを伝える
「ダメ!」と大声で怒ったり、無理やりやめさせたりする前に、まずは「走りたいのかな?」「走るのは楽しいよね」と子どもの気持ちを受け止めましょう。それから「ここでは人にぶつかると危ないからね」「ここは走る場所ではないから歩こうね」と、走ってはいけない理由をきちんと伝えます。
大切なことを伝えるときは、きちんと子どもの目を見て、真剣な声や表情で話しましょう。丁寧に、くり返し伝えていけば、1~2歳の子どもでも理解します。
子どもの「走りたい」という気持ちを受け止めてもらうことで、子どもは「お母さんは自分の気持ちをわかってくれた」と安心します。自分の気持ちが尊重されていると感じられれば、走ってはいけないことも穏やかに受け入れられるようになります。
子どもを公園や広場など安全に走ることができる場所に連れて行って、気が済むまで走らせてあげるのもいいでしょう。これをくり返すことで、子どもは走ってもいい場所、いけない場所の区別がつくようになります。
- 走り回る子どもは運動の敏感期にあるだけで、悪いことをしようとしているのではない。
- 気持ちを受け止めてから、危険なことややってはいけないことを真剣に伝える。
- 走りたい、体を動かしたいという子どもの気持ちが満たされる場所や遊びを提案する。
大人も「叱らなきゃ」と考えると肩に力が入り過ぎたり、つい感情的に怒ってしまいがちです。子どもが安全に、楽しく日常生活を送るために、必要なことを「伝えよう」と考えれば、ポジティブに子どもと向き合うことができるようになるのではないでしょうか。
年齢別

子どもの力を伸ばす
入園までにご家庭で身につけたい3つのこと
幼稚園や保育園に通うようになると、これまで家で大人が代わりにしていたことも、園では子どもが自分ですることになります。はじめて母子分離をした子どもが、自分の身支度を自分でできるようになるためには、家庭でどのようなサポートが必要なのでしょうか。

子どもの力を伸ばす
「伸びる力を育てる」プレゼントをクリスマスに贈る
クリスマスやお誕生日のプレゼント。スポンジのようになんでも吸収できる年齢の子どもこそ「伸びる力を育てる」贈り物をしませんか? 1~4歳の子どもの力を伸ばすプレゼント選びのポイントをご紹介します。