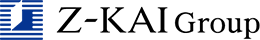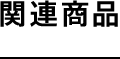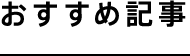環境づくり
子どもがはさみを使いたがるときは、巧緻性を育てる良い機会
子どもがはさみを使いたがるときは、巧緻性を育てる良い機会
2019.6.27
2~3歳ごろになると、「はさみ」に興味を持ち始める子どもが増えてきます。危ないからと遠ざけてしまわず、子どもの手のサイズに合ったはさみと専用の紙を用意して「切りたい!」という子どもの意欲に応えましょう。
はさみで指先の調整力や社会性を学ぶ
モンテッソーリ教育では、「日常生活の練習」として、2歳前後から、はさみを使い始めます。
はさみを開閉したり、線に沿って切ったりすることで、「手や手首の調整力」が洗練されていきます。同時に、刃先は人に向けない、受け渡すときは刃の側を持ち、持ち手を相手に差し出すなど、安全で正しいはさみの扱い方を通して、社会性を身につけることもできます。
はさみは子どもの手の大きさに合ったサイズで、弱い力でスムーズに切れるように設計された、子ども用はさみを選んであげましょう。開閉を補助するバネがついているものや、刃がガードで覆われているものを選べば安心です。

では、はさみで何を切らせるのがよいのでしょうか?
指を満たすことで、心も満たされる
アイ・シー・イー幼児教室や、ICEモンテッソーリこどものいえでは、子どもの発達段階に合わせて切る練習ができる「はさみきり台紙」を使っています。

子どもの手で持ちやすいサイズで、適度な厚みとコシのある紙を使っているので、持ったときにふにゃふにゃせず、切りやすいのがポイントです。はさみで切るところは太線で描かれているので、子どもにもわかりやすいでしょう。
大人がゆっくりとお手本を見せたら、刃をチョキンと一度閉じるだけで切り落とせる「1回切り」からスタート。最初はイラストの間の線がないものを切り、つぎにイラストとイラストの間の線を1回切りで切り落とします。切り落とした紙片は大切な作品です。受けるためのトレーを用意しましょう。
はさみきり台紙は、チョキチョキと二度開閉する「2回切り」、長い直線を切る「連続切り」、「曲線切り」と少しずつレベルアップしていきます。さらに、波線やうずまきなどの曲線を連続して切ったり、複雑な絵柄や対称図形の重ね切りができるようになります。
幼児期は、指先を上手に使う力=巧緻性が最も発達する時期だといわれています。また、「指を満たすことで、心が満たされる」というように、この時期に好きなだけ手や指先を使うことで、達成感が生まれ心が落ちつき、自信を持って意欲的に物事に取り組めるようになるなど、次の成長にもつながります。
子どもがはさみを使いたがるときは、指先を満たす良い機会だと考えましょう。子ども用のはさみや、はさみきり台紙を用意して、大人はそばで見守るだけでよいのです。
- はさみを子どもから遠ざけず、サイズの合った子ども用を与える。
- はさみきり台紙があれば、子どもの発達に合わせて切る練習ができる。
- 手をたくさん使うことで、心が満たされて次の成長につながる。
年齢別

環境づくり
ウィルス感染症予防のために、子どもに手洗いの習慣をつけるには?
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として「手洗い」が推奨されています。ところが「子どもが手洗いを嫌がる」「何度言っても自分からやらない」という悩みもよく耳にします。子どもに手洗いの習慣をつけるには、どうすればいいのでしょうか?

環境づくり
子どもが突然怒り出すのはどうして?
子どもが2~3歳になると、些細なことで、急に怒り出したり、泣き出したりすることがあります。いつもとちがう靴を履かせようとした、お母さんのマグカップをお父さんが使った、幼稚園の帰りにいつもとちがう道を通ったなど、この時期の子どもにとって「いつもと同じ」は、とても重要な意味があるのです。

環境づくり
子どもは本当は静かで落ち着いた空間が好き
集合住宅に住んでいると、ご近所の手前、子どもの声や足音などにも気をつかってしまいます。「どうしたら静かにしてくれるの?」と頭を悩ませる人もいるかもしれませんが、子どもは実は静かな環境が大好きなのです。