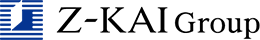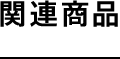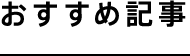環境づくり
ウィルス感染症予防のために、子どもに手洗いの習慣をつけるには?
ウィルス感染症予防のために、子どもに手洗いの習慣をつけるには?
2020.10.5
新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として「手洗い」が推奨されています。ところが「子どもが手洗いを嫌がる」「何度言っても自分からやらない」という悩みもよく耳にします。子どもに手洗いの習慣をつけるには、どうすればいいのでしょうか?
自分で手洗いができる環境を用意する
手洗いを嫌がる理由は、子どもによってさまざまです。
正しい洗い方がわからない、蛇口に手が届きにくい、石鹸がうまく使えない、水の温度や石鹸の感触が気に入らないなど……。本当は自分でやりたいのに、大人に抱きかかえられて無理やり洗わされることも、嫌がる理由かもしれません。
幼稚園や保育園には、子どもの背の高さに合わせた洗面台があり、石鹸や手拭きタオルも使いやすい場所にセットされていることがほとんどです。しかし家の洗面所は大人に合わせた形状になっているので、子どもにとっては使いにくいこともあるでしょう。

「自分で手洗いできるように手伝う」という気持ちで、まずは子どもの目線に立って、手を洗いやすい環境を整えていきます。
洗面台の前には、子どもが自分で持ち運べる、安定した踏み台を用意しましょう。子どもの手が届くテーブルに洗面器を用意して、そこで手を洗うという方法もあります。
石鹸は子どもの手の届きやすい場所に置きます。大きすぎて泡立てるのが難しいようなら、小さい石鹸を用意したり、子どもの手のサイズに合わせて石鹸を切ってもいいでしょう。
手拭きタオルは子ども専用のものを手の届く場所に吊るし、使用後のタオルを入れる場所も決めるなど、手を洗う一連の動作を、子どもが自分でできるように工夫してください。
手洗いの動作を一つずつ、ゆっくりと見せる
環境が整ったら、次は正しい手の洗い方を子どもに伝えます。
大人はふだん何気なくやっている手洗いですが、実はこんなに多くのプロセスがあります。
両手をぬらす
石鹸を泡立てて付ける
手のひらを洗う
手の甲を洗う
指と指の間を洗う
手首を洗う
爪の間を洗う
石鹸を洗い流す
水滴をきる
手を拭く
モンテッソーリ教育には、日常生活の動きを大人が目の前でやって見せて子どもに伝える「提示(提供)」という考え方があります。プロセスを一つずつ区切って、ゆっくりやって見せて子どもも正しい所作を身に付けていきます。
最初は上手にできなくても、くり返し行うことで習得していきます。大人はさりげなくサポートしながら見守りましょう。
子どもが興味を持って取り組む活動のことを、モンテッソーリ教育では「お仕事」と呼びます。数あるお仕事のなかには「手を洗うお仕事」もあります。
「ICEモンテッソーリこどものいえ」でも「手を洗うお仕事」は、子どもたちにとても人気があります。教師の提示を見ながら、何度もくり返すことで、2歳の子どもが指と指の間や手首までしっかりと洗うようになります。本来、子どもにとって手洗いは興味深く、魅力的な作業なのです。
この機会に、大人も子どもと一緒に正しい手の洗い方を見直してみてはいかがでしょうか。
『受験によく出る生活習慣』では、手洗いはもちろん、靴を脱ぐ、服をたたむ、などの日常生活の動作をわかりやすいイラストで丁寧に解説しています。モンテッソーリメソッドをベースに、子どもが自分のことを自分でできるようになるための「教え方の本」なので、受験の予定がないご家庭にもおすすめです。
- 子どもが自分で手を洗いやすいように、家庭での環境を整える
- 手洗いのプロセスを一つずつ区切って、目の前でゆっくりやって見せる
- 最初は上手にできなくても、大人は見守りながらサポートする
年齢別

環境づくり
子どもが突然怒り出すのはどうして?
子どもが2~3歳になると、些細なことで、急に怒り出したり、泣き出したりすることがあります。いつもとちがう靴を履かせようとした、お母さんのマグカップをお父さんが使った、幼稚園の帰りにいつもとちがう道を通ったなど、この時期の子どもにとって「いつもと同じ」は、とても重要な意味があるのです。

環境づくり
子どもがはさみを使いたがるときは、巧緻性を育てる良い機会
2~3歳ごろになると、「はさみ」に興味を持ち始める子どもが増えてきます。危ないからと遠ざけてしまわず、子どもの手のサイズに合ったはさみと専用の用紙を用意して「切りたい!」という子どもの意欲に応えましょう。

環境づくり
子どもは本当は静かで落ち着いた空間が好き
集合住宅に住んでいると、ご近所の手前、子どもの声や足音などにも気をつかってしまいます。「どうしたら静かにしてくれるの?」と頭を悩ませる人もいるかもしれませんが、子どもは実は静かな環境が大好きなのです。