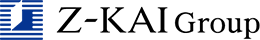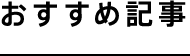子育ての悩み
スプーンやおもちゃを落としたり、
投げたりするので困っています。
スプーンやおもちゃを落としたり、投げたりするので困っています。
2018.11.4
子どもがスプーンやおもちゃを手当たり次第に床に落としたり、放り投げたりすることがあります。大人は「いたずらばかりで困る」と思うかもしれませんが、これはいたずらではなく、子どもの手や指の発達を助け、動きを獲得するために必要なことなのです。
手の動きを獲得しようとする大切な行動です
1歳から3歳くらいまでの未就園の子どもは、物を落としたり、投げたりすることが大好きです。大人は「なぜこんな乱暴なことを何度もやるのだろう」と思うかもしれません。
でも、この時期の子どもには、大人を困らせようとか、いたずらしたいという意識はありません。自分の手を使っていろいろなことを探求したり、確かめたりしているのです。
たとえば、落とすという動作。
スプーンを握っていた指を開くと、スプーンが床に落ちます。自分が手を動かすことで物が落ちるという現象が面白くて、何度でも落とします。
投げるという動作はさらに高度です。
指先で物を握った状態で腕を後ろから前に振り、前に来たときに指を開いて初めて、物が前に飛ぶのです。
子どもは、落としたり、投げたりする手の動きや、それによって起こる現象に興味津々で、手の動きを獲得しようとしています。とにかく面白くて仕方なくて、何度でもその動きがしたいのです。モンテッソーリ教育では「運動の敏感期」と呼んでいますが、運動機能だけでなく、脳や神経の発達にも深く関わっています。
投げてもいいもので楽しい遊びに
子どもはまだ、投げていい物といけない物の区別ができていません。
スプーンを投げたときは「これはスプーンだから投げません」
ボールを手渡して「これはボールだから投げてもいいよ」など、
まだ言葉を話す前の1歳から、投げてもいい物と、いけない物の区別をくり返し伝えていくことは大切です。
その上で、やわらかいボールやお手玉、風船など、家の中で投げても安全で、大人もストレスがたまらない物を用意して「物を投げたい!」という欲求を満足させてあげましょう。
箱やかごを用意して、そこに投げ入れるようにすると、大人も楽しめるゲームになります。
- 子どもが物を投げたり、落としたりするのは手の運動を獲得するのに大切な行動。
- 投げていい物、良くない物の区別はくり返し伝えていく。
- ボールや風船など投げてもいい物を用意して、投げたい欲求を満たす。

年齢別

子育ての悩み
withコロナ時代を親子で穏やかに過ごすには?
新型コロナウイルス感染症の拡大で、当たり前だった日常が突然失われ、先の見えない不安の中で過ごしています。そんな時代に親は子どもとどう接し、どんな心がけが必要なのでしょうか? アイ・シー・イーモンテッソーリこどものいえのモンテッソーリ教師に話を聞きました。

子育ての悩み
Q 子どもが1人で遊んでばかりでお友達と遊べません
児童館や公園に遊びに行ったり、幼稚園や保育園での集団生活が始まると、子どもは他の子とも関わるようになります。そんな中、1人遊びばかりでお友達と遊ばなかったり、おもちゃや遊具を譲れなくてけんかになったりすると、親としては心配になりますね。

子育ての悩み
Q 3歳を過ぎても自分でトイレに行けません
子どもが3歳になったり、幼稚園の入園が近づいてくると「早くトイレトレーニングを完了しなければ」と不安になったり、思うように進まずイライラしてしまうこともあるかもしれません。いつかは外れるものなので、まずはゆったりと構えましょう。モンテッソーリ教育のトイレトレーニングの考え方をご紹介しましょう。