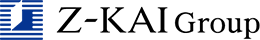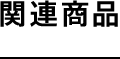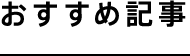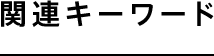子育ての悩み
withコロナ時代を親子で穏やかに過ごすには?
withコロナ時代を親子で穏やかに過ごすには?
2020.8.31
新型コロナウイルス感染症の拡大で、当たり前だった日常が突然失われ、先の見えない不安の中で過ごしています。そんな時代に親は子どもとどう接し、どのように心がければよいのでしょうか? 「ICEモンテッソーリこどものいえ」の教師に話を聞きました。
非常時もできるだけ「いつもと同じ」環境を
今回のように、誰も予想していなかった非常事態が起こると、「あれもできない、これもできない」と、できないことを数えて不安を募らせたり、「子どもにこれをさせなければ」と、焦ってしまう人も少なくありません。
まずは大人が冷静に、心を落ち着けることが大切です。
どんなに大変な状況もいつかは必ず落ち着く日がくると信じて、あせらず、無理をせず、平常心を保ち、子どものためにできることを一つずつ行いましょう。
たとえば、日常の生活だけでも「今までと同じ」にすることも大人の大切な役割です。
「子どもが突然怒り出すのはどうして?」でくわしく触れていますが、2~3歳の子どもの場合は「いつもと同じ=秩序感」を尊重することで安心して、心が落ち着いていきます。
登園がなくても、いつもと同じ時間に起きて着替える。食事や遊び、入浴の時間、方法、順番などもできるだけ同じにしてあげましょう。
人が多く集まる公園に行けないときでも、外気に触れる時間を作りましょう。人が少ない場所や時間帯を見つけてお散歩をしたり、ベランダでシャボン玉遊びをするなど、外の景色を眺めるだけでも、気分が晴れやかになります。
体を動かすのが好きな子どもなら、新聞紙を思い切りちぎったり、丸めて投げるなど、家の中でもできるアクティブな遊びを一緒に考えましょう。子どもはどんなときも、自分で工夫して遊びを考え、楽しむことができる力を備えています。
子どもが今、何をやりたがっているのか、何に興味を持っているのかをよく観察して、寄り添ってあげられるといいですね。

非常時でも前向きに、子どもの意欲や自主性を尊重することが大切
コロナ禍でガラッと変わってしまった生活で、ストレスを抱える子どもが増えていると報道などで見聞きしますが、臨時休園を経て「ICEモンテッソーリこどものいえ」に久しぶりに登園してきた子どもたちの表情はとても穏やかで、落ち着いていました。
保護者に休園中の様子を訊ねると、次のような言葉を聞くことができました。
「子どもがいつもお手伝いをしたがったので、私もとても助かりました。一緒にパンを焼いたり、料理をしたりして楽しい時間を過ごしました」(3歳)
「一日中一緒に過ごすことで、子どもが自分で洋服をたたんだり、食器を片付けたりする様子をそばで見守ることができました。ここまで自分のことができるようになったのかと感心しました」(2歳)
「自分でコップを洗ったり、食後にお皿を片付けるなど、休みの間も園と同じ生活習慣で過ごしていました。身支度も早くできるようになって、日々の積み重ねの成果を感じています」(2歳半)
このほか、お父さんが在宅勤務になったことで、家族全員で過ごす時間が増えて、子どもがうれしそうだった、という声も多く聞かれました。今回のような非常事態も「子どもとともに過ごす時間が増えた」と前向きにとらえる保護者が多かったことが印象的です。
外出が制限されて、大好きな友達や祖父母になかなか会えない、自由に外遊びができないことは、確かに残念なことかもしれません。でも、子どもは案外「お母さん、お父さんのそばにずっといられてうれしい!」と思っていたりします。
子どもの自主性を尊重して見守ることで、大人も子どもも穏やかに、そして豊かな時間を過ごせるのではないでしょうか。
- まずは大人があせらず、無理をせず、平常心を持つ
- 子どものために、家の中だけでも、なるべくいつもと同じ環境を用意する
- 非常時も前向きにとらえて、子どもの意欲や自主性を尊重して見守ることが大切
年齢別

子育ての悩み
Q 子どもが1人で遊んでばかりでお友達と遊べません
児童館や公園に遊びに行ったり、幼稚園や保育園での集団生活が始まると、子どもは他の子とも関わるようになります。そんな中、1人遊びばかりでお友達と遊ばなかったり、おもちゃや遊具を譲れなくてけんかになったりすると、親としては心配になりますね。

子育ての悩み
Q 3歳を過ぎても自分でトイレに行けません
子どもが3歳になったり、幼稚園の入園が近づいてくると「早くトイレトレーニングを完了しなければ」と不安になったり、思うように進まずイライラしてしまうこともあるかもしれません。いつかは外れるものなので、まずはゆったりと構えましょう。モンテッソーリ教育のトイレトレーニングの考え方をご紹介しましょう。

子育ての悩み
スプーンやおもちゃを落としたり、
投げたりするので困っています。
子どもがスプーンやおもちゃを手当たり次第に床に落としたり、放り投げたりすることがあります。大人は「いたずらばかりで困る」と思うかもしれませんが、これはいたずらではなく、子どもの手や指の発達を助け、動きを獲得するために必要なことなのです。